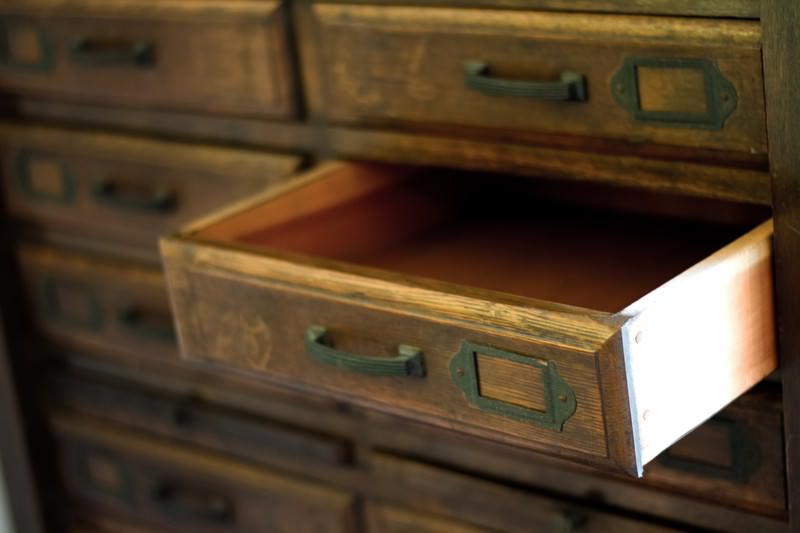所得税・住民税の定額減税についてどのような制度なのかご案内いたします。
——————————————————————————————————–
1.定額減税とは
令和6年分の所得税と個人住民税に対して行われる減税施策のことです。
2.控除される金額
(所 得 税) 本人と扶養親族人数×30,000円
(個人住民税) 本人と扶養親族人数×10,000円
※上記扶養親族には所得税の控除で含まれない、16歳未満の方も含まれます。
※控除しきれなかった額については、令和7年1月以降に繰り越して控除されませんが、
別途給付金制度がございます。
3.控除を受けられる人
(1)令和6年分の所得税の納税者であること。
(2)日本国内に住所を有する個人または引き続いて1年以上居所を有する個人(居住者)であること。
(3)令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下であること。
4.給与所得者、年金受給者、個人事業主についてそれぞれの減税方法
(1)給与所得者
6月給与に係る源泉所得税で控除されます。引ききれない金額については7月から12月の給与源泉所得税、年末調整、確定申告にかけて順次控除されます。
※主たる給与の支払者のもと(甲欄)でのみ控除されます。
※源泉徴収票の摘要欄に減額済み額が記載されます。
(2)年金受給者
6月に支給される公的年金の源泉徴収分から控除されます。
引ききれない金額については給与所得者同様7月から12月、確定申告にかけて順次控除されます。
(3)個人事業主
第1期予定納税額から控除されます。
引ききれない金額は、第2期予定納税で、最終的には確定申告で控除額を清算されます。
5.具体的な減税のされ方
(本人と扶養親族2名の場合で、各月の源泉徴収税額が35,000円の場合)
定額減税所得税控除額:30,000×3名=90,000円
6月 7月 8月 9月以降
控除前税額 35,000円 35,000円 35,000円 35,000円
▢▢▢▢▢▢▢▢▢↓▢▢ ▢▢▢↓▢▢▢ ▢▢↓▢▢▢ ▢▢↓
控除後税額 0円 0円 15,000円 35,000円
6.住民税の控除
(1)給与から引かれる方(特別徴収)は、6月分は控除されず、年間の金額から7-5月分の11カ月間で均一に控除されます。
(2)自分で納付する方(普通徴収)は、控除額が引かれた納付書が届きます。
ご不明な点ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。